倭は卑しいという意味ではない。祈りと調和に生きた民の名です。
倭人
倭人は、調和を重んじる人々でした。
古代の日本には、女王が国を統べる習わしがあり、女王は自ら神に仕え、祈りの力で人々を導き、信仰にもとづいて道徳を説き、国を鎮めていました。
『魏志倭人伝』には、卑弥呼の術を鬼道と記します。ここで言う「鬼」は、後世に定着した怨霊・怪物ではなく、本来は祖霊・自然の精霊を指す語と読めます。
すなわち鬼道とは、祖霊と自然に感謝を捧げ、祈りによって共同体を結び直す術でした。
藤原氏の時代になると、律令体制の整備とともに祭祀は国家の装置へと制度化され、祈りの核は相対的に後景に退きます。秩序の安定という利点はあった一方で、「鬼」を怪異とみなす解釈が強まり、「倭=卑小」へ傾く物語が広がった可能性があります。
ここには、統治の正統性を物語として整える必要が作用し、巫女的統治の権威を歴史の奥へ退かせ、制度と血統に正統の座を移すという再配置が進んだ、と見ることができます。
本来、倭とは「人が草木に委ねる姿」。
私はこのように理解しています。女性が自然の恵みに感謝し、天に祈りを捧げる姿そのものです。
倭は侮蔑の標ではなく、祈りと調和を生きる民の呼び名です。
忘れられたものは、失われたのではありません。
言葉を整え、祈りを正し、祖霊と自然に手を合わせるその一呼吸から、記憶は灯り直します。
倭呼吸塾は、藤原氏の時代に形成された物語の偏りを知らせつつ、対立ではなく調和をもって、祈りの国の本来の形へ静かに還してゆきます。

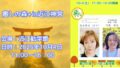
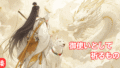
コメント